毎年2月~3月になると、確定申告の話題で少し憂鬱な気分になる…という方はいらっしゃいませんか?
「今年もギリギリになってしまった…」 「会計入力が全く進んでいない…」 「もしかしたら、もっと税金を安くできたかもしれない」
フリーランスや個人事業主の方、副業で収入を得ている会社員の方にとって、確定申告は避けて通れない大切な義務です。そして、多くの方が「年が明けてから準備すればいいや」と考えがちですが、実はその考えが「損」につながる可能性があることをご存知でしょうか。
来年2026年に行う「2025年分確定申告」で後悔しないために、専門家が「秋から始めるべき理由」と具体的な準備について解説します。
なぜ「今から」始めないと損するの?
理由は大きく分けて2つあります。
1.節税対策の多くは「年内」がリミットだから
これが最も重要なポイントです。節税につながる制度の多くは、1月1日から12月31日までの支払いや手続きが対象となります。つまり、年が明けてから「やっておけばよかった!」と気づいても、もう手遅れなのです。
- ふるさと納税:年末はサイトが混み合ったり、人気の返礼品が品切れになったりしがちです。ご自身の寄付上限額を確認し、計画的に利用するなら今が最適な時期です。
- iDeCo(個人型確定拠出年金):掛金が全額所得控除の対象となる強力な節税策ですが、加入手続きには1〜2ヶ月かかることも。年内の掛金支払いに間に合わせるには、秋からの行動が必須です。
- 生命保険料控除、小規模企業共済など:これらも年内に支払った掛金・保険料が控除の対象です。
年が明けてからでは、打てる節税の選択肢が大幅に減ってしまいます。
2.心の余裕が「正確な申告」と「本業の成果」を生むから
確定申告シーズンは、多くの方にとって本業が忙しい時期と重なります。そんな中、1年分の会計入力に追われるのは、大きなストレスです。
慌てて作業をすると、計上できるはずの経費を見落としたり、入力ミスをしたりする可能性が高まります。結果的に、本来払う必要のない税金を納めてしまうことにもなりかねません。
今のうちから準備を進めておけば、心に余裕が生まれ、申告内容をじっくり見直す時間ができます。何より、本業に集中できる環境を維持できることが大きなメリットと言えるでしょう。
今日からできる!確定申告準備の3ステップ
では、具体的に何をすれば良いのでしょうか。難しいことはありません。まずは以下の3つを確認・実行してみましょう。
STEP 1:会計ソフトに「こまめ」に入力する 1年分をまとめて入力するのは大変な作業です。会計ソフトを導入している方は、「週末に15分だけ入力する」など、習慣づけてしまいましょう。こまめに入力することで、現在の売上や利益をリアルタイムで把握でき、納税額の予測や経営判断にも役立ちます。
STEP 2:今年の利益を予測し、「節税策」を検討・実行する 9月にもなると、年間の利益がある程度見えてくる頃です。おおよその利益が分かれば、納めるべき税額も予測できます。その上で、「ふるさと納税をあといくらできるか」「今年は小規模企業共済に加入しようか」といった具体的な節税プランを検討し、年内に実行しましょう。
STEP 3:【重要】消費税の届出、忘れていませんか? インボイス制度の開始以降、消費税の納税義務者(課税事業者)になった方も多いはずです。消費税に関する届出も**「年内が提出期限」**のものが多く、提出するか否かで納税額に大きな差が出ることがあります。
- 簡易課税制度選択届出書:原則課税か簡易課税かを選択する重要な届出です。業種によっては、簡易課税を選択する方が有利になるケースがあります。適用を受けたい年の前年12月31日までの提出が必要です。
- 消費税課税事業者選択届出書:免税事業者があえて課税事業者になる場合に提出します。大きな設備投資などがあり、消費税の還付が見込まれる場合に検討します。
これらの届出は一度提出すると原則2年間は変更できません。ご自身の事業状況をよく確認し、有利な方を選択できているか、この時期に必ず見直しましょう。不明な点があれば、税務署や専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
確定申告は、単なる納税手続きではなく、ご自身の1年間の事業活動の集大成です。そして、その準備は未来への投資でもあります。
「節税は、年内が勝負」
この言葉を心に留めて、ぜひ今日から少しずつ準備を始めてみてください。来年の春、心穏やかに確定申告を終え、気持ちよく新年度をスタートさせましょう。
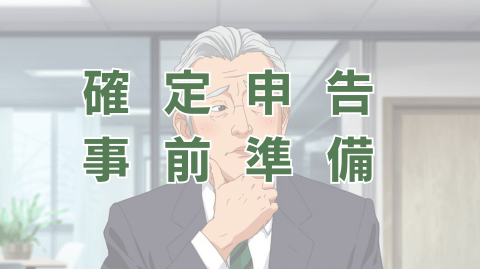
コメント